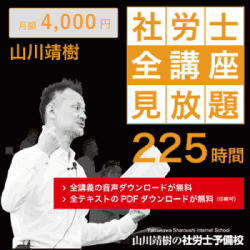次のステージを目指して、あらたな資格を目指そうかと思いはじめました。
先週、行政書士の本試験日でした。受験生のツイートや、予備校の難易度評価YouTubeに刺激を受けています。
資格試験を挑む判断基準
あらたに国家試験に挑むならば、相当の覚悟が必要です
目指す目的は何なのか?
自身にとって資格が、あらたな付加価値となるのか等々
メリット/デメリットを抽出
メリットとデメリット(ORリスク)とのバランスで受験するかを検討しています
メリットは資格がコレクションとならず、ビジネスに活かせるのか
(=稼ぎにつながるかどうか)等
メリットはたくさん書き出せると思います
私の場合ならばメリットは、社労士との親和性、あらたな仕事の需要拡大になるのか、
自分自身で行政書士業をやるワンストップメリットと、実績のある先生に現状とおり連携するのが良いのか、この見極めにつきます。
勉強の覚悟をもてるためには、リスクを許容できるかどうか
ここが一番大事ですね
仮にメリットが小でも、リスクがゼロなら受験価値はあります。
簡単な資格なら、リスクはテキスト代ぐらいと、少し時間がかかること
ほぼリスクはないレベル
憧れの国家資格となると試験の難易度が高くなります。
難易度が、比較的目指しやすい宅建士でも、独学でコストをおさえられても
勉強時間300時間ぐらいは必要となります。
1回で受かる確率も当然100%ではありません。
仕事しながら狙える代表格で合格率、平均勉強時間を比較
宅建:約15% 300時間~
行政書士:約10% 600時間~
社労士:約6% 1000時間~
宅建から社労士で合格率の差があるものと、大きな差でもありません
これは真の合格率が見えてないので、同程度に見えているだけです。
例えば最難関の弁護士は合格率30%ぐらい
数値だけなら、司法試験が一番簡単になってしまいます
もちろん、そんな事はありませんね。
受験されている方のレベルによってかわります
弁護士はハイレベルな人達の中での戦い
行政書士は、年齢、学歴で受験制限がない戦いです
各資格間で基準が統一されてないので、一概に数値だけで比較できません。
自身の経験値を活かせる科目かどうかも難易度に影響します
各分野(法律系、理系等)、学習の傾向(理解型、暗記型)との相性も大事
例えば社労士ならば、
全科目を学習を完投したレベルの受験生だけで、合格率をみると
30%ぐらいあるともいわれます
科目の難易度も、物理や数学に比べたら、身近な日本語の法律でテキストを読めばわかるレベルで難しくありません。
難易度が高くなっているのは、試験範囲が広すぎで10科目もある、さらに無限に出題範囲が広がる一般常識の難問(合計点の足切り基準が厳しい)が原因です
自身にとっての本当の難易度を見極めることが、
未経験者にとって一番難しいのです
合格への近道を探す
久々に大物の資格、行政書士に挑戦しようと思ったら、
真の難易度が、私にわかりません
また難易度を下げる方法
どのテキストが最短合格への道なのか
予備校を使うべきか・・・
予備校のパンフレット、合格者ブログ、行政書士YouTube等を見まくってますが、
調べれば調べる程、迷うばかり
はじめて勉強をしたいと思った時、不安な気持ち、悩みを思いだしました
予備校の値段も3万円台から20万円台と幅が広い
1発合格が保証されるなら、100万円でも安いと思いますが、
値段に比例して合格率が高くなるわけでもない
合格体験記から、予備校を選ぼうにも、自身の性格は他人とも違う
学校との相性は千差万別
現時点での私の対策は
まず、試験との相性を確認するところから始めることにしました
超基本テキストを買ってみて、勉強を継続できそうか?(好きになれるか?)を見極めます。
科目の全体概要、試験制度の仕組みがわかれば、挑戦が無謀でないかがわかります。
超基礎知識を身に付ければ、どの道が最短になるか比較をできる考えています。
あと超基礎を全科目で完投してしまえば、
ここでやったのに勉強を辞めるのはもったいないと思う性分なので、
引くに引けずに勉強を本格始動に進めるかなとも考えてます。
社労士試験に挑むかどうかを、決める時にも、お世話になった
はじめの一歩シリーズをポチリりました
社労士試験の制度、難易度まとめはこちら
👇
行政書士試験の合格への近道(テキスト、独学対策、予備校比較等)
がまとまったら、当ブログで公開したいと思います。

それではまたあした
未来の自分に投資しましょう!
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。 👇