「わかっているつもり」と「説明できる」の違い この壁をどう乗り越えるか
「理解しているつもりだったのに、いざ説明しようとすると言葉に詰まる。」そんな経験はありませんか?
テキストを読み、問題を解き、解説を確認。一通り学習を終えたはずなのに、いざ誰かに説明しようとすると、思ったように言葉が出てこない。この現象は、多くの人が学習の過程で陥る「わかっているつもり」の罠です。
私自身も、まさにこの壁に直面しました。しかし、言語化を意識した学習法を取り入れることで、知識を確実に定着させ、試験対策にも活かすことができました。この記事では、その具体的な方法をお伝えします。
わかっているつもりの罠
学習を進める中で、「理解できた」と感じる瞬間は多くあります。しかし、その「理解」は本当に十分なのでしょうか?
一問一答形式で黙々と解くならできていた、非常に簡単なこ論点でも、突然、相手から質問され、口頭で説明しようとすると、うまくできないことがあります。
この経験から、「ただ知識を頭に入れるだけでは不十分であり、自分の言葉で説明できる状態になって初めて、本当の理解に到達するのだ」と開業当初に痛感したことがあります。
言語化の威力
黙読や暗記だけでは知識は、お客様への説明に使えない、試験での得点に繋がらないと、生きた知識になってないんです。自分の言葉で説明し伝わっときに、知識が整理され理解が深まり、身に付くことになります。
実践方法
最も重要な論点を一つ選び、架空の初学者に説明するつもりで、頭の中で言語化。つまずいた部分はメモを取り、後で確認するようにします。
驚くべきことに、説明しようとすると、自分の理解が曖昧な部分が次々と浮き彫りになるのです。「この部分、どうしてこうなるんだっけ?」と、自分で疑問を持つことで、知識の抜け漏れを発見しやすくなりました。
効果的な取り組み方
言語化の習慣を身につけるために、次のような方法を取り入れました。
勉強した内容を短い間隔で、思い出し、説明する練習をします
-
通勤時間を活用し、頭の中で説明練習をする
-
重要な論点を選び、順番に説明してみる
-
つまずいたポイントを記録し、帰宅後に復習する
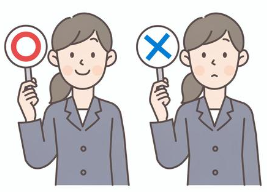
このサイクルを続けることで、知識の定着率が大幅に向上しました。
言語化と試験の関係性
試験委員の立場になって考えてみましょう。受験者の理解度を測るには、どのような問題を作るでしょうか?
そう、「社労士として正しい説明できる力」を問われてるはずです。
択一式は、論点の正誤判断をする力、選択式では正しい文章を完成、組み立てる力が試されます。試験に合格するためには、単に知識をインプットするだけでなく、アウトプットの練習を通じて、しっかりと言語化できる状態にすることが不可欠なのです。
まとめ
学習の過程では、知識のインプットが欠かせません。しかし、それだけでは十分とはいえず、アウトプットを通じた言語化の練習が、知識を確実に定着させる鍵となります。
☆御礼☆
最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、皆さんの学習のヒントになれば幸いです。参考になりましたら、ぜひシェアや応援をよろしくお願いいたします。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️




 合格革命 社労士 ×問式問題集 比較認識法(R)で択一対策 2024年度 [×式問題×作問者思考×比較認識法で合格力アップ!](早稲田経営出版)](https://m.media-amazon.com/images/I/51E2Q-ps1QL._SL500_.jpg)

