社労士を受験を検討されてる方から質問されるナンバー1は、
「何時間で合格できますか?」です。
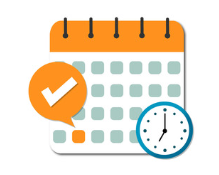
予備校やネットの勉強時間情報
少ない方で800時間、大多数が1000時間と回答されています。
実際に合格された方(知り合い、Twitter含む)の情報では、
初学、法律系の初心者で500時間で合格した猛者も実際にいます。
合格レベルに達成する時間は?
個人の能力、経験により差があるのは勿論ですが、
10科目にわたる社労士試験勉強において、
一通り理解できる最低時間が800時間前後
基本論点を確実に得点する。7割以上正解できれば合格レベルに達します。
社労士受験は勉強時間×運?
試験はマークシートなので、800時間合格できる可能性はあります。
500時間でも運があれば、合格できそうな難易度です。
実は運と言われる要素が社労士試験の難易度を上げています。
合格レベル=確実に合格できることが、確約できない試験方式があります。
難易度を上げる合格基準点について
科目毎に基準点が設定されています。
合計点が9割でも、科目の基準点が1点足らなければ、試験をパスできません。
1点に泣く試験と言われます。
中でも特に厳しいのが、午前に実施される選択式試験の基準点
1科目5問あり、3点以上の得点する必要があります。
6割以上で基準点クリアですが、問題数で言えば3点失点したらアウトです。
選択式の科目で、一般常識の2科目(労働一般、社会保険)に、
予備校のテキストに掲載されてないような難問がでまくります。
過去には、5点満点が、3万以上の受験生がいて、9人しかいなかった難問がありました。
※平均点がわるい場合は、救済措置があり、3点基準が下げられることはあります。
救済条件については
👇
今年のボーダー予想では社会保険の一般常識で、2点救済になっても良いぐらい難しい問題でしたが、結果として、15年振りに全科目で救済なしとなり、
合格率が、過去3番目に低い5.3%になってしまいました。
1000時間をかけて全科目を平均的に勉強ができていれば、(苦手科目をなくす)
合格できる合計7割はとれるようになってきますが、
選択式だけは、確実に3点をとることが非常に難しい科目があります。
模試でA判定の方でも、受験前は皆ナーバスになります。
3年、4年、5年連続・・・で1点に泣かされた受験生を大勢います
(知り合いにもいるぐらい身近な話です)
3年目で合格なら良い方です。現役カリスマ社労士先生でも、3年ぐらいかかってる方は普通にいます、合格年数と社労士との実力は、まったく別物です。
(落とすための試験を突破した得点力と、社労士としての知識力、センスは別)
令和5年 第55回 社労士試験を受験される方へ
社労士試験は、勉強時間数に比例して知識量は増えますが、合格率は高くなりません。
社労士試験の無限地獄にハマらないためにも、1年で1000時間を目安に学習計画を立てて、1年で突破する気合を持って勉強の密度を高めて挑んでください。
余裕をもって2年計画で勉強しても、選択式の一般常識科目があるかぎり、
合格確実性がみえてきません。かえって2年目のプレッシャーが重なり、きつく感じるだけです。
冒頭の質問「何時間で合格できる」は?
選択式の基準点があるかぎり、運しだいかもしれません・・・
ちなみに、令和4年は、選択式で奇問がなく、難しい問題ではありましたが、
確実に勉強をしていた方で、冷静な判断があれば、各科目3点はとれるレベルでした。
ある意味、今年は選択式は運がなくても、実力で突破できる試験でした。
今年に受験できた方は運を持っていたかもしれません・・・
(オール3点以上とは1点のケアレスミスも許されないことなので、基準点を超えるハードルが非常に高いのには変わりありません)
合格レベルになる時間数は?
1000時間あれば、十分に合格を狙えます。
合格するのは難しいとは言え、1000時間程度勉強ができれば、
合格可能性が得られる試験でもあります。
独占業務がある国家資格の中では勉強のコスパは良い試験と言えます。
実は難しいのは、忙しい中で勉強を継続すること、続けられて1000時間の壁を超えられれば、あとは合格の順番待ちと考えれば、必ず合格できる試験です。
多少合格に時間がかかっても、蓄えた知識は裏切りません。
社労士としてのスタートダッシュに繋がりますから・・・
ぜひ、挑戦してみてください。社会人にとって取れたら、最高の武器になりますよ
【参考】令和5年受験対策
令和5年版予備校の選び方
初学者向けのテキスト選び方
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️
初学の方なら、「はじめの一歩」から
TACの入門書から始めたら、
独学者が愛用してる、TACの通常版への発展もスムーズです。
合格者が多い市販書です。






